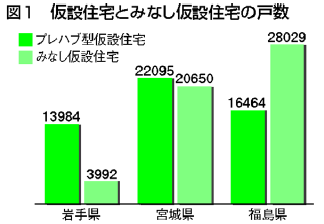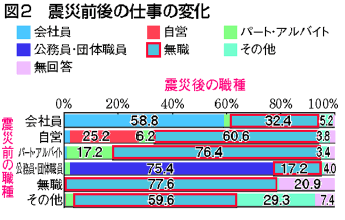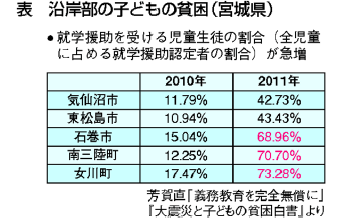被災から2年を経て 「人間の復興」に必要なものは
いまも続く被災地の困難。「復興のためにいま必要なのは、医療や介護・福祉など社会サービスのインフラ整備」と福島大学の丹波史 紀准教授(行政政策学類)は話します。震災発生直後から有志で「福島大学災害復興研究所」を立ち上げ、支援や調査、提言活動を実施。中でも福島第一原発に 近い福島県8町村の避難住民への実態調査は注目されました。3年目の課題を聞きます。(木下直子記者)
福島大学災害復興研究所
丹波史紀さんにきく
東日本大震災は被災者数、被害面積でも甚大でした。また、被害をリカバリーする土台の社会が、一九九五年の阪神淡路大震災時とは、比べものにならないほど弱くなっています。第一次産業を中心に成り立っていた地域が、冷遇され高齢・過疎化しています。
自治体リストラで公務員が減らされ、行政機能が縮小していることも土台の弱体化の一因です。復興計画を作る職員が一人体制の自治体も。「過去の災害の教 訓を生かしていない」などの指摘もありますが、実情は「アドバイスを受け止める土台がない。手が回らない」というものです。このことは、被災住民のサポー ト不足にも端的に表れていると思います。
■「調査」からみた被災者
震災から半年後、福島第一原発に隣接し避難を余儀なくされた八町村(浪江町、双葉町、大熊 町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村)の全住民を対象に、自治体の協力も得て実態調査を行いました。二万八一八四世帯に郵送し、一万三五七六世帯 が回答。この規模の調査はなく、二〇一一年一二月の原子力賠償審査会に私が呼ばれるほど注目されました。
「若い避難者ほど帰郷の意志が低い」(図3)ことが中心に報道されましたが、注目はそこだけではありません。原発災害は自然災害では想定できなかった(1)広域避難(2)長期化(3)避難の多様化・孤立化という事態を生んだのです。
〈広域避難〉
住民も行政機能も別の自治体に頼らざるをえず、家族も離散しました。調査では、避難回数三~四回が四七%、五回以上の人は三五%おり、最多は四八回。これは生活や産業の基盤を失った人が大量に生み出されたことを意味します。宮城県でも県外避難者は九〇〇〇人です。
〈長期化〉
福島県では、二年たっても約一六万人が避難生活中です。宮城県や岩手県もあわ せると三一万人超に及びます。ふるさとに戻る見通しが立たないことが、生活再建を大きく阻み、被災者を苦しめています。また、避難の長期化が帰還への意志 を奪うことにも。調査では、高齢者ほど帰還に待てる年数が短く(六五歳以上は七割以上が「三年以内」と回答)、一方、若い層ほど「戻る気がない」という回 答が多数で、子育て世代の放射能への不安が表れていました。
〈多様化・孤立化〉
大規模災害では仮設住宅が建設されますが、今回、民間賃貸住宅を国が借り上げ、被災者に供与する「みなし仮設」ができました。福島県では仮設住宅を上回ります(図1)。宮城県でも都市部を中心に同じ傾向で、仙台市では応急仮設住宅のうち、みなし仮設は約八五%。多賀城市でも約七五%。
みなし仮設はプレハブ仮設より快適ですが、問題は孤立しやすいこと。自治体が個人情報の扱いに慎重すぎることも一因で、被災者向けの情報や民間の支援が届きにくいのです。
■生活、子どもの貧困
暮らしはどうか。「復興特需」の求人はありますが、ミスマッチです。「仕事を選ぶなんて、被災者はわがままだ」との言われ方もしますが、違います。
職種別に震災前後の就労状況を調査してみると、震災前に会社員だった人で三割、自営業で六割、パートで八割近くが無職になっていました(図2)。パートの多くが女性で、いまある土木や除染作業などの求人に合わない。しかも有期雇用なので、生活を再建できる仕事ではありません。
被災者が誇りをもち、仕事を通じて生活再建を果たせる手立てが必要です。復興政策は被災者を雇用した企業への補助金や、被災地に進出した企業への税制上 の優遇措置など「雇用側」向けが中心で、被災者への直接支援は少ない。これが根本問題だと思います。
子どもたちの状況も見過ごせません。宮城県沿岸部では就学援助が急増。全児童に占める利用者は全国平均で一六%(一一年度)ですが、表のように六〇~七〇%超という事態です。
3年目以降の課題
復興三年目の中心に据えるべきことは―。大規模な復旧工事は経済効果があるように見えますが、全体からみれば、医療や介護、福祉など社会サービスのインフラ整備の方が価値が高いのです。そこが弱いと、住民の帰還が遅れる要因にもなります。
「もともと地域が抱えていた課題を震災が加速させた」と、よく言われます。高齢化や過疎化は、全国各地で起きつつある問題ですから「被災地で解決をすす めた教訓は、日本の地域社会の再生にもつながる」―。そんな視点が必要です。
■被災地が求める医療
医療に関して、福島県では放射能による健康不安が大きい。「高度医療センターを作り、がん になれば高度医療で治す」との方針では解決しません。先端医療に数百億円をかけても、県民には遠い話です。日常的に住民の相談に応じる体制や、住民と向き 合う医療人の確保、地域の医療機関がしっかり働ける環境づくりが有効です。新潟県中越地震で被災した旧山古志村では、保健師が住民の状況をつかんで良い働 きをしました。
また、医療や福祉職の確保と養成には時間がかかります。子どもたちが、そうした職種にすすめるような支援策も良い。住民の補助金に使っていた予算を、医 療や介護関係に進学する高校生の奨学金にあてた自治体もあります。
■復興の近道は住民の参画
今回の災害は行政だけでは乗り越えられません。復興計画の策定や実施に、住民がいかに参画するか。「この災害を住民とともに乗り越えていく」視点が大事です。
「復興計画作りは少数の幹部ですすめた方が早い」という自治体もあります。しかし、多くの住民が参加する方が、遠回りに見えて近道なのです。「自分たち が作った計画だ」という自覚が生まれ、行政と住民が協同して災害を乗り越える基盤にもなる。
私が関わっている浪江町では、住民一〇〇人で復興計画を作りました。計画の柱の一つが「帰る、帰らないに関わらず、全員の生活再建をめざす」。帰還しな い人もささえるのは、自治体には苦渋の 決断ですが、町民の分裂を生まずに復興に向かうための一番の共通項がそこでした。
もう一つの柱は「ふるさと」です。浪江の子ども一七〇〇人にアンケートをとりました。四割が県外避難、半数が家族離散という子どもの約八割が「浪江の友 だちと会えない」ことを困りごとにあげました。 そして、自然豊かな浪江町への愛着を綴ったのです。
揺れていた大人たちは、ふるさとを放棄しない決意を固めました。「生きている間に解決しないかもしれないが、次の世代にふるさとを引き継ぎたい」と涙な がらに語った区長もいました。こうして町の復興計画は、一人ひとりの生活再建を掲げつつ、ふるさとを引き継ぐ努力をしよう、との内容になりました。
その後、住民たちはNPOを作ってカフェを開業したり、伝統の焼き物を復活させて技術を継承しようと動いています。被災者自身が復興を遂げなければ、という気運の芽生えを感じます。
ふるさとを再生するのは誰か? と考えると、住民なのです。復興の責任を果たしていない東電や国への要求も、自分たちがどういう町に帰りたいかという観 点でとりくむべきです。「住民自治」が改めて問われています。
(民医連新聞 第1544号 2013年3月18日)