響き合う健康観 広島で国際HPHカンファ
写真・野田雅也
聞き手・八田大輔(編集部)
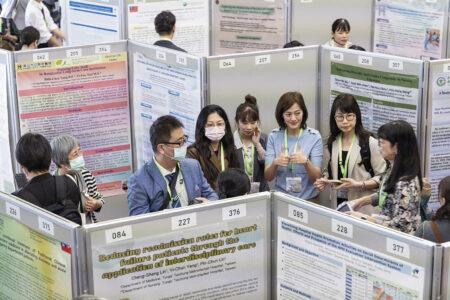
各国の参加者が活発に意見交換したポスターセッション
第30回国際HPH※1カンファレンスが昨年11月、広島市で行われました。
34カ国から研究者や医療従事者、市民ら約800人が参加。
そこで見えてきた世界の健康観は、民医連の理念と共通するものでした。
国際HPHカンファレンス日本組織委員会事務局長を務めた
舟越光彦医師(福岡・千鳥橋病院)に話を聞きました。
今回の国際HPHカンファレンス(以下カンファ、概要は左ページ別項)は「健康の公正性を目指して~医療機関と介護事業所の貢献」がテーマでした。
「公正性」はすべての人々が健康であるための前提条件です。全体会で講演したリチャード・ウィルキンソン※2氏は、格差が大きく不平等な社会であればあるほど、人口の大多数の健康と幸福に害があることを明示しました。
健康には地域環境や公共政策、社会風土が強く影響します。今回のカンファでは、地域の中の公正性や医療制度の公正性、さらには性的マイノリティーや外国籍住民など、医療の枠を越えた公正性についても報告されました。
海外の取り組みで特に注目した点は?
たとえばカナダのギャリー・ブロック氏(トロント大学准教授)は、家庭医という立場からホームレスの人々に直接手を差し伸べるだけでなく、社会を変えるために街頭に立って演説もする。公正な社会の実現を重視するHPHの姿勢そのものです。また海外の発表者は、取り組んだ内容の数値化や言語化、発信力に優れていると感じました。
世界のHPH加盟事業所と民医連の共通点を教えてください。
HPHの目的は病院内での治療に加え、地域の健康水準をヘルスプロモーション※3を通して高めることにあります。民医連はSDH※4の概念やオタワ憲章が提唱されるずっと前から、労働環境や社会的背景が健康に与える影響に気づき、地域での活動や行政への提言を行ってきました。この点で「民医連の健康観は世界の常識と合致する」と言えます。
欧州のHPHは、病院の中で患者やその家族に対してヘルスプロモーションを行うのが主流。対して日本や台湾といったアジア諸国では、院外に出向いて住民健診などの活動を行う傾向があり、欧州と比べて医療機関と地域の垣根が低いのが特徴です。
今回のカンファで得た発見は?
改めて共同組織の先進性を実感しました。ポスターセッション444演題のうち、住民からの発表は日本の共同組織だけです。住民が自発的に健康作りのネットワークを組織し、専門家と協力して健康を維持、改善する。日本独自の活動で、海外の参加者からも注目されました。(5ページ別項参照)
健康であることは一人一人が持つ人権であり、ヘルスプロモーションにおいて住民の主体的な参加は不可欠。共同組織は世界から見ても先進的な存在です。その有効性をデータに基づいて評価し、エビデンス(根拠)を示していくことがこれからの課題です。
新入職員へ向けてのメッセージをお願いします。
〝The personal is political〟(個人的なことは政治的なこと)という言葉があります。困難を抱える人のパーソナル(個人的)な事柄を通して、その背景にあるポリティカル(政治的)な事象に気づくこと。その感性を持ってほしいと思います。
そのためにも目の前の患者さん、利用者さんの話をよく聞いてください。「困った患者」と片づけず、その人の抱える困難の原因に思いを巡らす。考えるためのヒントは、先輩職員や共同組織のみなさんが教えてくれるはずです。
また、今回のカンファは被爆地である広島で行われ、開会式では日本被団協の児玉三智子さんが自らの被爆体験を証言しました。WHOをはじめ、国際機関の多くは第二次世界大戦の反省から発足し、戦争を二度と起こさないことが最大の使命。民医連だけでなくさまざまな医療団体と手を取り合い、健康の基盤である「平和」を守ってほしいと思います。
※1 HPH Health Promoting Hospitals & Health Services(健康増進活動拠点病院および事業所)の略。病気の治療だけでなく地域全体の健康水準向上に取り組み、健康なまちづくりと幸福・公平・公正な社会の実現に貢献することを目的とした事業所のこと。国際HPHネットワークは1989年発足。日本HPHネットワークは2015年に結成され、123の病院や介護事業所などが加盟している。
※2 リチャード・ウィルキンソン 英国ノッティンガム大学名誉教授。健康格差研究の世界的権威。
※3 ヘルスプロモーション WHOが1986年のオタワ憲章で提唱した健康戦略。「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義される。
※4 SDH Social Determinants of Health(健康の社会的決定要因)の略。
トピックで振り返る国際HPHカンファ
被爆地で初開催 国際HPHカンファレンス(以下カンファ)の開催地は欧州が中心で日本は初めて。偶然、被団協(日本原水爆被害者団体協議会)のノーベル平和賞受賞直後に広島で開催され注目を集めた。カンファ初日に広島で被爆した児玉三智子さん(被団協事務局次長、写真)が講演。「核兵器を作るのも使うのも人間。核兵器の使用を止めること、なくすことができるのも私たち人間です」と核兵器廃絶を訴えた。
複合的な危機 フラン・バウムさん(オーストラリア)は相次ぐ紛争、気候変動、感染症、格差と貧困の進行など世界は複合的な危機の只中にあり、貧困層がより苦しめられていると強調。SDH(健康の社会的決定要因)を踏まえた戦略を提唱した。
健康の公正性 カンファのテーマは「健康の公正性」。「公正」とは社会的に不利な条件に置かれた人でも、等しく権利を獲得できるように働きかける言葉。民医連の理念である「無差別・平等の医療と福祉の実現」に近い概念。
会話は全て英語 プレナリーセッション(全体会)の14演題、パラレルセッション(分科会)とミニ口演合わせて180演題、ポスターセッション444演題は、原則として全て英語で発表(一部日本語通訳あり)。
日本医師会も カンファの日本組織委員会顧問には、日本医師会や日本歯科医師会、日本薬剤師会の会長、日本プライマリ・ケア連合学会や日本ヘルスプロモーション学会の理事長らが名を連ねた。
次回はスウェーデン 第31回国際HPHカンファレンスは、2026年5月にスウェーデンのマルメで行われる。
班会は社会資源
文・新井健治(編集部)
国際カンファには、共同組織(健康友の会会員や医療生協組合員)の仲間も多数参加しました。倉敷医療生協(岡山)副理事長の早川髙子さんに聞きました。
「医療生協が長年続けてきた班会やサロンの活動が、国際的な会議の場で改めて理論的に位置づけられたと実感しました」と早川さん。早川さんは国際カンファのパラレルセッションで、班会に参加して歩行能力が改善した事例を発表しました。
事例は87歳の女性が週1回(40分)の班会に参加して体操を続けた効果を検証。最初はよろよろ歩いていたのが、半年後、1年後と目に見えてしっかり歩行できるようになった様子を映像で紹介。女性は服装もおしゃれになるなど、心身ともに活発になりました。
ほかにも、75歳以上の高齢者25人が体操と茶話会の班会に参加することで、健康を維持できた事例も報告。「班会が介護予防の役割を果たしている」と強調しました。
高齢者のフレイル(加齢により心身が衰えた状態)予防には「食事」「運動」「社会参加」の3つが大切といわれます。早川さんは「班会は社会との接点」と位置づけ、組合員が3人いれば組合員以外の人も参加できるなど規約を変え、班会を地域に広く開きました。
コロナ禍でも屋外で体操するなど、可能な限り活動を継続。班会の数は2016年の479から増え続け、24年は700を超えました。
国際カンファに参加した諸外国からは、住民の自主的な健康づくりの発表はなく、共同組織は日本独自のものといえます。「ヘルスプロモーションとは知らずに医療生協の活動を続けてきましたが、世界の先進的な健康観と合致していることに気付かされました」と言います。
世界的に健康格差が広がるなか、班会は①社会との接点②身近な通いの場・居場所③健康寿命の維持・改善の場と位置付ける早川さん。「班会が時代が求めるソーシャルキャピタル(社会資源)の役割を果たせれば」と話しました。
いつでも元気 2025.4 No.401
- 記事関連ワード
- 国際HPHカンファレンス





