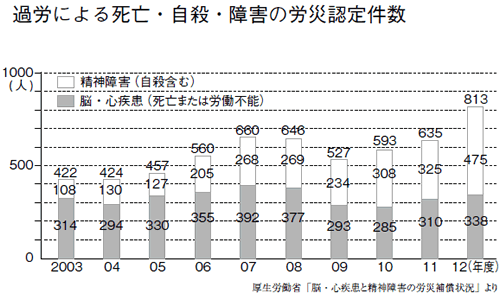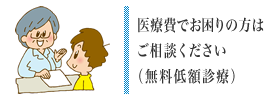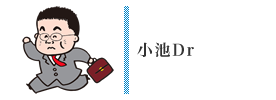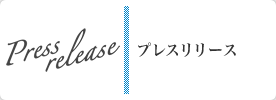いつでも元気
2014年3月1日
特集2 仕事と生活習慣病 働く者の健康を考える
健康・仕事に人間発達の観点を
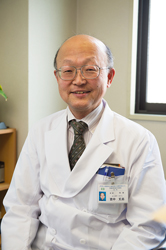 |
| 吉中丈志 京都民医連中央病院院長 NPO法人「メンタルサポート京都」理事長 |
昨年、全日本民医連は創立60周年を迎えました。労働災害や職業病(労災職業病)に対する医療や補償・再発防止などを求める運動は、民医連の歴史でも重要な分野です。
60周年を機に、労災職業病に対する医療と運動の観点から民医連での私の歩みを振り返り、未来につなげようと考えて執筆したのが、『仕事と生活習慣病』 (幻冬舎・税込七七七円)です。「働くことが健康に悪いと考えがちだが、働くことこそ健康の基本では」などと考えながら書くうちに、このタイトルが浮かん できました。働く者のいのちと健康を守る運動の中で多くの人たちと出会ったことが、出版の原動力になったことは間違いありません。
労災職業病の歴史を振り返る
私自身の経験ももとに、労災職業病の歴史を振り返ってみます。
■振動病・頚肩腕障害・腰痛・ じん肺
京都では東山トンネル(旧国鉄)の開通工事に携わった労働者や清水焼職人のじん肺に続き、振動病・頚肩腕障害・腰痛などの職業病に対する運動が1970年代にとりくまれました。私が学生時代アルバイトをしていた京都民医連の待鳳診療所も労災職業病にとりくんでいました。
労災職業病の診断法・治療法を模索しながら労働組合運動・民主運動・革新府政に大きく貢献しました。特定の作業・職場に対応した病気が多く、原因が見え やすいことが特徴でした。京都では労働組合・自由法曹団・民医連が、被災者・家族を支援する京都職業病対策連絡会議(職対連)を結成しました。
■過労死
1980年代になると過労死が社会問題化します。海外でも「KAROSHI」と報道され、高度経済成長の中での長時間・過密労働がクローズアップされま した。職対連の中に過労死対策医師団や過労死対策弁護団が結成され、私もマスコミで訴えました。テレビで訴えた際、トイレで桂三枝(現・文枝)さんといっ しょになり、「お互い大変ですなー」と言葉をかわしたのを覚えています。
過労死に至る病気は、くも膜下出血や脳出血などの脳血管障害や心筋梗塞・大動脈解離などが代表的です。長時間・過密労働が原因となって発症しますが、背 景に高血圧・糖尿病・脂質異常症(高脂血症)などの危険因子があることも少なくありません。特定の作業や職場で起こるそれまでの職業病とは異なるため、 「企業に責任はない」「個人の健康管理の問題」と主張されることが多く、私は裁判などで「異議あり」「過労死を引き起こした病気の危険因子に、長時間・過 密労働は入らないのか」と訴えてきました。
成人病は1996年に「生活習慣病」と改名されました。私は民医連新聞で「『生活習慣病』の呼称では、労働が病気を引き起こす視点が抜け落ちる」と批判 しました。その呼称の提唱者・日野原重明さん(聖路加国際メディカルセンター理事長)は、今回の出版にあたり「心と体が健康になる働き方。忙しい人にとっ て必読の書です」と推薦の言葉を書いてくれました。時代の変遷を感じます。
■慢性二硫化炭素中毒
京都民医連がユニチカのレーヨン工場(宇治市)で起こった慢性二硫化炭素中毒症(CS2)の問題にとりくむようになったのは、同じく興国人絹八代工場で の同中毒問題をたたかっていた熊本民医連からの通報(1983年)がきっかけでした。
被災者や家族、これを支える同僚・労働組合・地域住民の思いが運動を進めた原動力でした。たたかいのなかで京都民医連のあさくら診療所が、無産者診療所 建設運動のきっかけになった代議士・山本宣治ゆかりの地・宇治市に誕生しました。
「僕らは子どもたちに、次の世代にバトンを渡していくんですよね。そのとき、ちょっとでも良くした世の中を渡せないんやったら、何のために生きてきたん かわからんでしょ。それに僕らはいつでも一人やなかった。弁護士さん、お医者さん、いろんな人が一生懸命に支えてくれはった。だから、がんばれたんやと思 います」。会社の圧力に屈せずに証言した、ある労働者のことばです。
韓国でも日本の東洋レーヨン(現・東レ)から輸入した工場設備がもとでCS2中毒が起こり、補償を求める運動が起こりました。この運動がきっかけで、民 医連と韓国の労働者・医療者との海峡を越えた交流が始まりました。今、民医連と交流している緑色病院(ソウル市・久里市)は、CS2被災者への補償を求め るたたかいから生まれた病院です。
■過労自殺とメンタルヘルス
1980年代末のバブル経済崩壊後、日本は弱肉強食の構造改革に突入し、90年代後半から現役労働者世代の自殺が急増します。自殺者数は年間3万人を超 え、韓国と並んで自殺率の高い国になりました。はじめは「熟年世代」が多かったのですが、2000年代に入ってからは若い世代の自殺が目立つようになりま した。2012年に3万人を切りましたが、同じ傾向は続いています。
自殺は氷山の一角で、すそ野には広範な人々の間に広がっているメンタルヘルス(心の健康)の不調があります。背景には失業、不安定雇用などがあります。 とくに2008年のリーマンショック以降は「ブラック企業」が跋扈し、ここ数年は過労死・過労自殺が増えています。昨年、NHK「おはよう日本」は「長時 間労働などが原因で死亡したり自殺を図ったりして労災認定された人の数は、昨年度800人を超え過去最多になった」と報じました(グラフ)。
厚生労働省が「過労死基準」とする月80時間以上の残業を許容している事業所も多く、全国の事業所のうち64%で残業に関する法律違反があります。経済成長時代の過労死が、デフレの時代に復活したのです。
今、労働組合に持ちこまれる相談でメンタルヘルスの事例が増えています。京都では2011年、「はたらくものの命と健康を守る京都センター」と職対連 で、労働者のメンタルヘルスを支援するNPO法人「メンタルサポート京都」を発足させました。現在「“ストップ! 過労死”実行委員会」などが中心とな り、過労死防止基本法の制定を求める運動が全国でおこなわれています。
■がん
2005年にクボタの工場(兵庫)でアスベスト(石綿)による労働者の健康被害が明るみに出ました。その後、健康被害は家族・周辺住民にまで広がってい ることがわかりました。アスベストで起こる代表的な病気は、肺がんと悪性中皮腫です。
2012年には大阪の印刷工場で胆管がんが多発しました。厚生労働省は緊急調査をおこない、印刷機の洗浄に使用されていた化学物質(ジクロロプロパン、 ジクロロメタン)が原因と判断し、労災と認定しました。古くは染料・塗料に含まれる化学物質(ベンジンなど)がもとで起こる膀胱がんが有名でしたが、あら ためて職業起因性のがんに焦点があたるようになったのです。
最近では「30年以上夜勤労働をしている女性労働者は、乳がん発症リスクが2倍になる」という研究報告が注目されています。デンマークでは看護師の乳が んが職業病と認定され、予防措置がとられています。発がんを抑制するメラトニン(脳から分泌され、体内時計を調節する役割も持つ)が夜間労働によって減少 するためと考えられています。
喫煙や過度の飲酒も発がんの原因とされますが、これらも仕事と深い関連があります。仕事と関係のない生活習慣はないと言ってもよいでしょう。少なくとも がんは、現在判明している以上に職業が影響しているのではないかと思います。
仕事を生活習慣に位置づけて
こうして見ると、現代の仕事はさまざまな病気の発生要因だと言えそうです。では、仕事から解放されれば健康は促進されるのでしょうか?
しかし「仕事からの解放」とは、現実的には失業であり、失業は健康を損なうというのが世界の常識です。世界保健機関(WHO)は健康を損なう社会的な要 因として、長時間・過密労働、社会的な格差、ストレス、社会的排除とともに失業を挙げ、健康促進のためにこれらを減じる公共政策が重要だと指摘していま す。あたり前ですが「仕事からの解放」は、悠々自適の生活を意味しません。
私たちは生活の少なくとも3分の1の時間を仕事にあてています。生活習慣病を予防するには、生活の大きな部分を占める仕事の仕方を、健康を増進する方向 へと転換することが必要です。仕事を生活習慣の中に位置づけて「もっと仕事の仕方を重視して考えてみよう」というのが、『仕事と生活習慣病』の結論です。
健康を考える4本柱
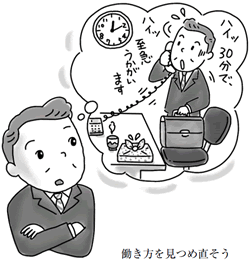 |
| 働き方を見つめ直そう |
「身体的、精神的、社会的に良好な状態」を「健康」とするWHOの提唱は、世界中で広く受け入れられています。私はこれに「人間発達」の観点を取り入れることが必要だと思います。人間的な営みという観点を重視したいからです。
人間的な営みは、仕事・生活(衣食住など)・文化・成長(発達)の4本柱から成り立っています。働く者の健康を4本柱それぞれについて、身体的・精神 的・社会的な健康度(指標)が良くなっていくことと考えたいのです。私にとって労災職業病の運動は健康権保障を求めるとともに、4本柱の大切さを学んだ運 動でもありました。
「労働が人間をつくった」と言われるように仕事は健康に影響を及ぼす第一の要素です。しかし、働きがいを得にくいのが現代社会。多くの人が体と心をすり減らし、働く喜びや成長を実感するどころではありません。
こうして健康は仕事から離れて「消費生活」に追いやられ、商品化された健康を買うしかない現状が蔓延しています。コマーシャルでは「健康を買いましょ う、急いで!」といった調子で、やせ細った健康のイメージが商品にすり替わっています。
働く者の健康を取り戻すためには、健康の豊かなイメージを浮かび上がらせる努力が必要だと痛切に感じています。ポイントは労働現場=仕事にあるのではないでしょうか。
人間的な仕事と健康を
過大な期待から、サービス業などに理不尽なクレームが寄せられることも増えていると言われています。
値下げ競争もいきすぎていると感じます。労働者が精魂つくして作った物やサービスをおとしめる側面があるからです。労働者が、消費する側に立つと態度が 豹変することも少なくありません。健康増進のためにも、お互いの仕事をおとしめるのではなく、高め合う関係が必要です。
韓国では「労働者に椅子を」という運動がとりくまれています。「客がいないときはコンビニ・スーパーの労働者が椅子に座れるように」という運動です。清 掃労働者など体が汚れる作業をする人が、帰宅前にシャワーを浴びられるようにしようという運動もあります。働く者の連帯で成果を生んでいます。
東日本大震災で「絆」ということばがはやりました。この絆を心だけではなく、社会のあり方としてとらえるべきです。私が経験してきた働く者の命と健康を 守る運動にはそのような絆があり、未来の豊かな健康と社会への希望があると感じます。
「活私創公」こそ働く者に求められる挑戦ではないでしょうか。疲労蓄積度チェックリスト(表)を活用して、健康を見直すことから始めましょう。疲労は自分で気がつかないことも多いので、家族や同僚によるチェックも大切です。『仕事と生活習慣病』の中には、家族によるチェックリストも掲載しました。班会などで活用してもらえば幸いです。
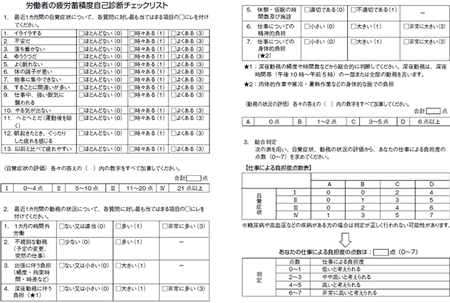 |
| (拡大) |
イラスト・井上ひいろ
いつでも元気 2014.3 No.269
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。